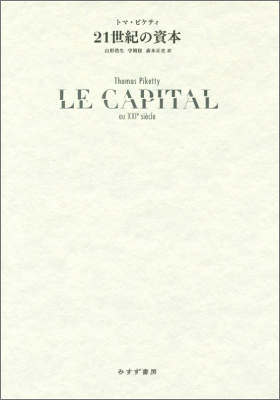経済学者ピケティの21世紀の資本です。難しいので箇条書きにします。
21世紀の資本箇条書き
- ピケティ『21世紀の資本』の主張:資本収益率 r が経済成長率 g より高いと格差が増大する。
- 浅田論文の主張:r > g は格差拡大の必要条件でも十分条件でもない。
- 必要条件:r > g でなければ格差は絶対に拡大しない。
- 十分条件:r > g であれば格差は絶対に拡大する。
- 反証方法:r > g でも格差が増えない事例や、r < g でも格差が増える事例を示す。
- r > g でも資本収益がその場で消費されると格差は増えない。
- r < g でも収益が蓄積されると格差は増えることがある。
- 新古典派モデルの結論:利潤分配率は r や g に依存しないため、格差は増えない。
- 新ケインズ派モデルの結論:r > g でも資産格差や所得格差は増えない。
- 論文の限界:現実の格差拡大を完全に説明するには不十分。
- ピケティの主張:実際の格差問題を優先して考えるべき。
- 数理モデルは仮説検証の一助だが、現実との整合性が重要。
- ピケティ以後の議論:格差の正当化や累進課税議論に影響。
- 範例:格差が現実に生じているかの検討が必要。
- まとめ:r > g が格差拡大の唯一の条件でないことは事実だが、格差問題は現実データの分析が鍵。
rとgの注釈
r(資本収益率)
- 定義: ある期間における資本の増加額を、その期間の初めにおける資本額で割った比率。つまり、資本がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す指標です。
- 意味:
- 投資の収益性: 株、不動産などへの投資によって得られる収益率を指します。
- 資本所有者の収入: 資本を所有している人(資本家)が、その資本から得られる収入の割合を示します。
- ピケティの主張における重要性: ピケティは、rがgを上回ることが長期的に格差拡大をもたらす要因の一つであると主張しています。つまり、資本が労働よりも高い割合で収益を生み出すことで、資本家と労働者の間の所得格差が拡大するという考え方です。
g(経済成長率)
- 定義: ある期間における経済全体の生産量の増加率。つまり、経済がどれだけ大きくなったかを示す指標です。
- 意味:
- 国民所得の伸び: 国民全体の所得がどれだけ増加したかを示します。
- 生活水準の向上: 一般的に、経済成長率が高いほど、国民の生活水準は向上すると考えられています。
- ピケティの主張における重要性: ピケティは、rとgの関係性に着目し、rがgを上回ることが長期的に格差拡大をもたらす要因の一つであると主張しています。つまり、資本収益率が経済成長率を上回ると、資本所有者の富がより速く増えるため、格差が拡大するという考え方です。
rとgの関係性
- ピケティの不等式: ピケティは、r > gという不等式を提唱し、この状態が長期的に格差拡大をもたらすことを主張しています。
- その他のモデル: 新古典派や新ケインズ派のモデルでは、rとgの関係性や格差との関係性について、ピケティとは異なる結論が得られています。
まとめ
ピケティの『21世紀の資本』では、資本収益率rが経済成長率gを上回ると、富の不平等が拡大するという主張がなされています。
資本収益率rとは、株や不動産などの投資によって得られる収益の割合のことです。
一方、経済成長率gは、経済全体の生産量が増加する割合を示します。ピケティは、r > gという状態が長期的に続くと、資本を持つ人々の富が労働者よりも速く増えるため、格差が拡大すると考えています。
以上の説は現代日本に当てはまっているような気がしますね。